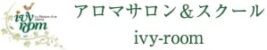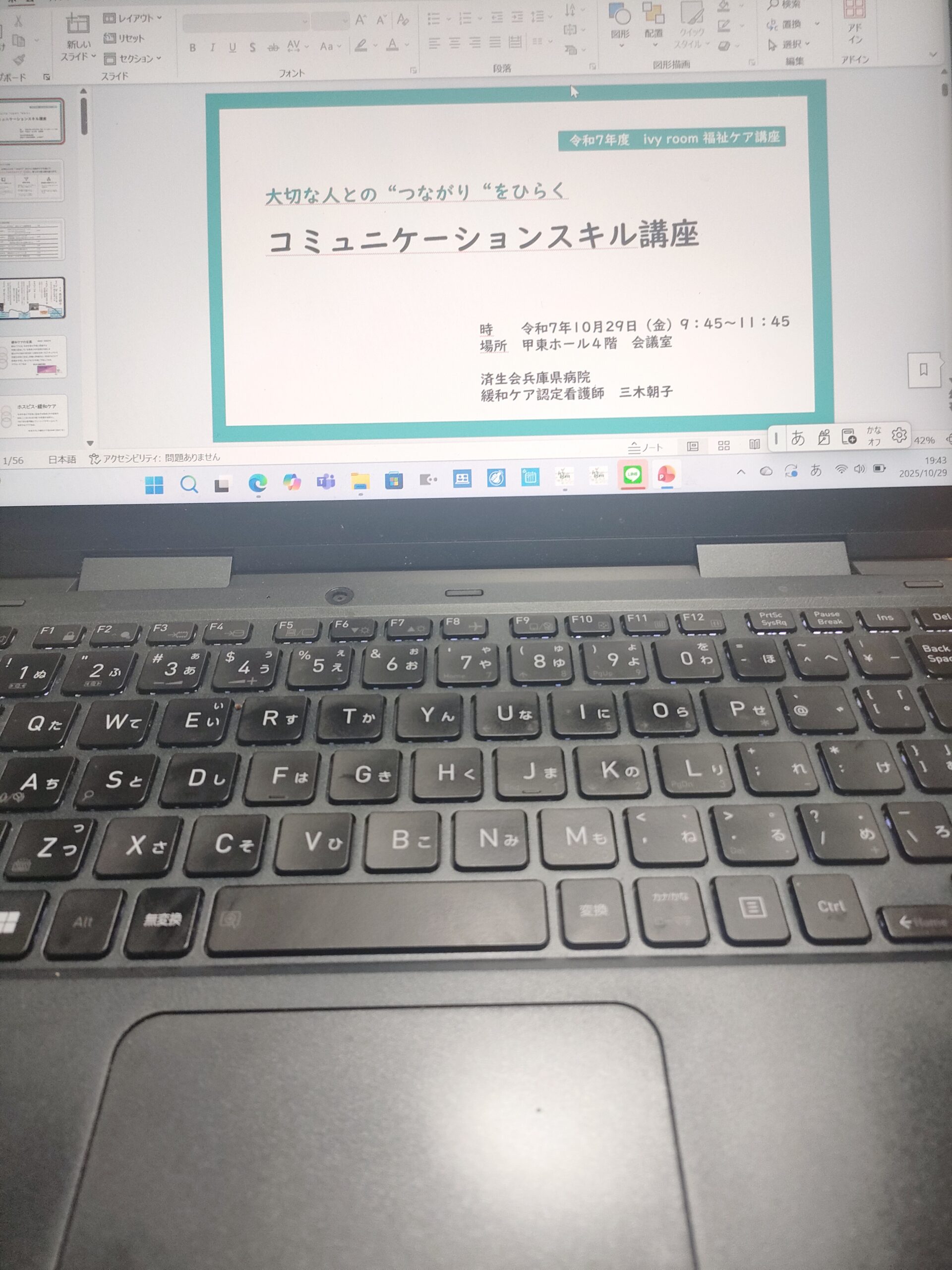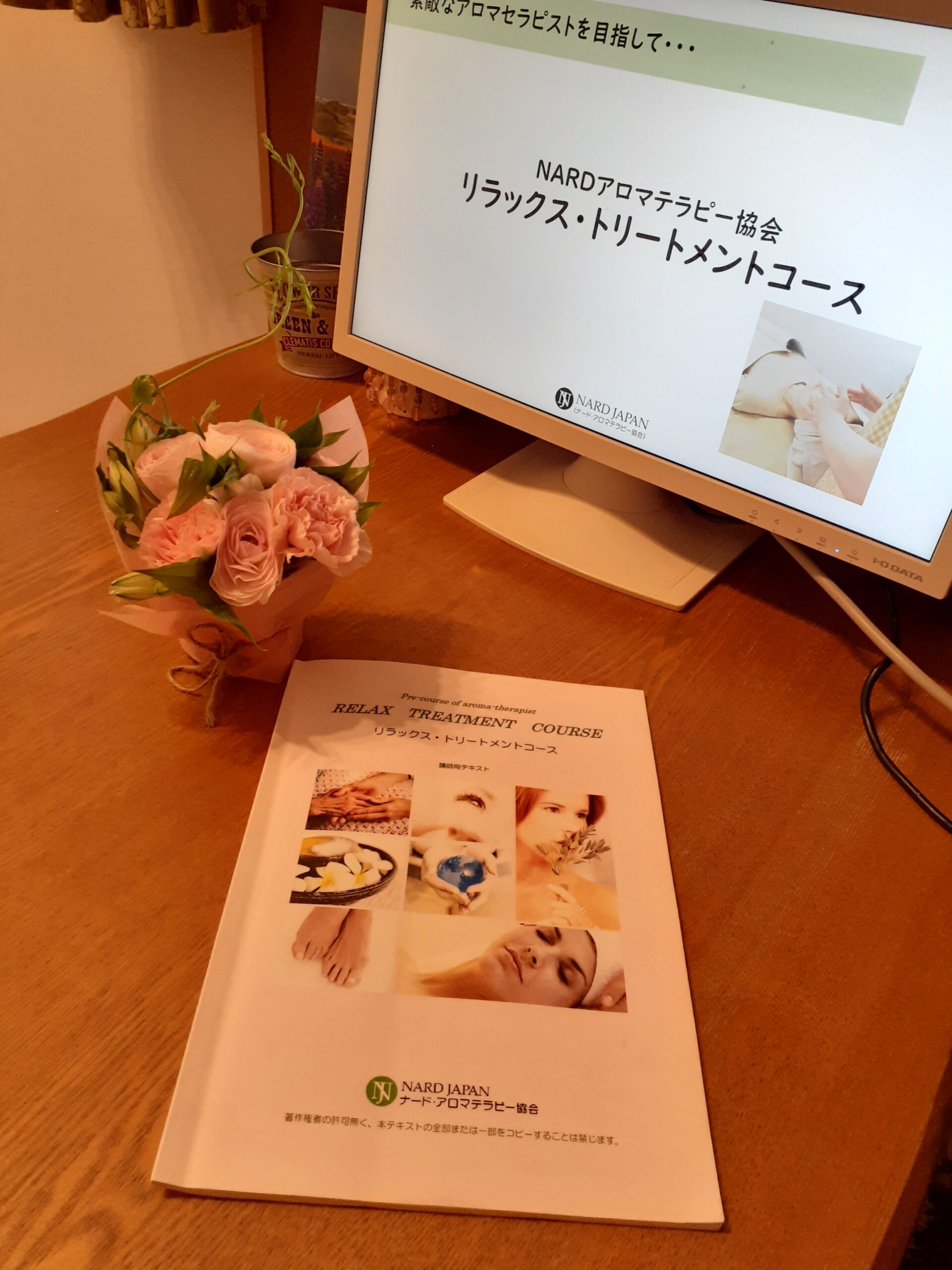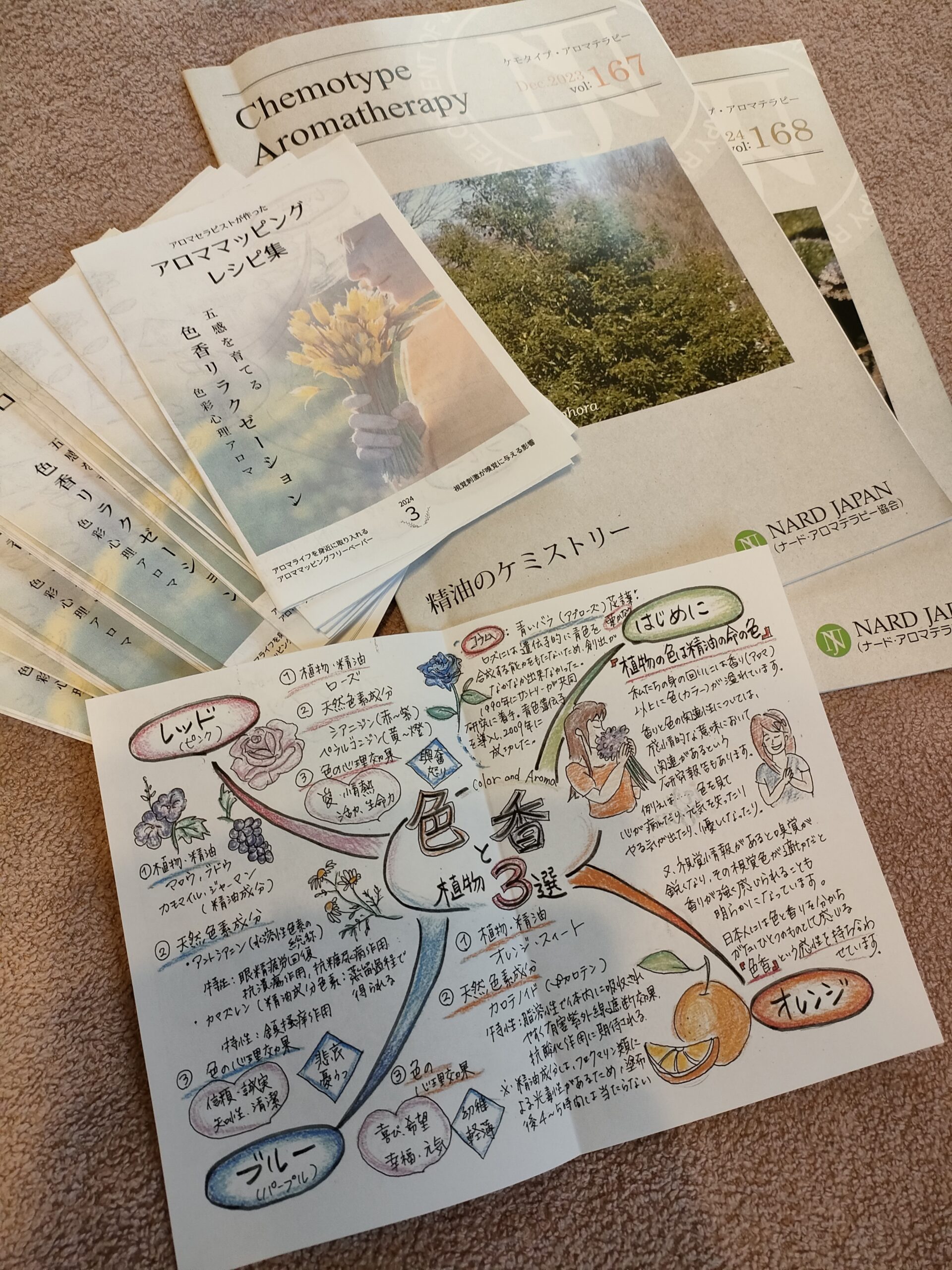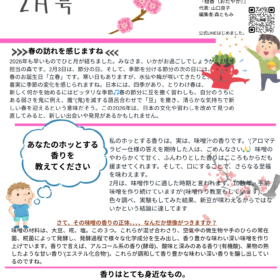コミュニケーションとは、相互の理解を感じあうためのもの
先日、セラピストとして活躍されていらっしゃる方を中心に、普段活動時に目の前の方とのコミュニケーションを図るためのヒントとして、済生会兵庫県病院 緩和ケア認定看護師の三木朝子先生をお招きし、
「コミュニケーションスキル講座」
を開催いたしました。
まずは、緩和ケア病棟における場所を想定した
・援助的なコミュニケーションを用いた優しい関わりかたを実践する。
・安心感を与える声かけで、ケアを導入することができる。
・スピリチュアルケアを理解し、ケアの中で取り入れられる。
を目的とした内容で、”その人らしさを引き出すケア”を実践し、いつものコミュニケーションを振り返り、今後に生かす事をそれぞれで見つけていただきます。
特に緩和ケア病棟でのこうしたアロマセラピストの活動には、”日本ホスピス緩和ケア協会HP”からも、
”生活を脅かす疾患に直面する患者とその家族のQOL(人生と生活の質)の改善を目的とし、さまざまな専門職とボランティアがチームとして提供するケアである
との定義から、必要性を感じていただいています。
まだ、”ボランティア”としての括りつけになっているには、少し考えさせられることもありますが、医療従事者の方の中でも私たちの存在価値を理解しつつ傾向もあり、今後の動向にも期待があげられます。
私自身も、こうした活動の中だけでなく、日々色んな方たちと接したり、向き合ったり、時には発信していく中でコミュニケーションについて良く考えさせられます。
一方通行でない、
「人間関係において情報や感情、考えを相手に伝え、相互理解を促進するための行為」
「言語や非言語手段を用い、相互の理解を目指す」
としての、どちらにも負担にならない関係作りが、本来のコミュニケーションであると考えており、だからこそ福祉活動においても、受け手側、与えている側の健全な関係性を作る必要性があると思っています。
私自身、講話から改めて
・非言語的コミュニケーションの必要性(相手を受け入れるまでの4つの壁として基盤となる共感的態度の大切さ)
・安心感を与える科学的根拠における触れ方
・相互に理解しあえるための段階的な歩み寄り方
について、腑に落ちること、気づきなどもあり、また人との向き合い方にもいろいろ考えさせていただいた良い機会でもありました。
参加者の方からも
・先生のお話を聴いたからこそさらに心の癒しにつながりました。
・とても有意義なお話を聴ける機会になりました。
・先生のお話はもちろん、参加者皆さまの発表にも心に残りました。
・いろいろ考えるきっかけになりました。
・「症例のひとつ」と無意識に見る癖がついてしまうと高飛車な接し方になるだろうし、共感しすぎて距離を縮めすぎると疲弊してしまう。その距離感が大事、相手に最大限敬意を払いながら、自分の出来る事を模索する・・・そんなセラピスト像が深いなとかんじました。
とても貴重な感想もありがとうございました。